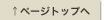塩竈の民話
「おじゃら浜の奇談」
明治の初めごろから、塩釜の外港として、経済文化の中心が石浜港に集まり、貨物船の出入りが、日増しに盛んになってきました。
船乗りたちも、全国から石浜に集まってきて(注1)きもいり肝煎の家の高橋安吉さんの世話になっていました。肝煎は、出入船の取締りやら、船員の雇い入れやら、海事のことまで任されていました。
この石浜に「せんちょう浜、おじゃら浜」という、昔火葬を行なった場所があります。他国の者が亡くなったりすると、必ずここで火葬にしたということです。
昔、かいこうまる海幸丸という船が、航海中に、三河(愛知県)の人で仙吉という船乗りが、釜石沖で急死してしまいました。数日後に仙吉の死体を乗せた船が、石浜港に入ったという届けが、肝煎のところにきて、肝煎高橋安吉方で、一切の手続きをすませると、ずいがんじ瑞巌寺からおしょうさんを呼んで、お葬式の用意をしました。
仲間の船員たちみんなで、火葬の準備も終わり、親しかった権吉と銀蔵のふたりが、火葬の世話をすることになりました。
ふたりは一晩中、線香をあげ、火葬のための薪をたきつづけました。
その夜は、静かな晩でしたが、薪や芝の燃え盛かる青白い炎、死体の焼ける異様なにおい、その間を黒い煙がうずを巻いて、まるで地獄絵のような恐ろしい光景でありました。
それでもふたりは、仲の良かった仙吉のために、口口に念仏を唱えながら、一心に薪をもやしつづけていました。
そのうち、夜もだんだんふけて、時間もかなりたったので、ふたりは、
「もう、そろそろ焼けだべなや。薪をたくのはやめてもいいんでねえがや」
と話していた時でした。今まで青い炎をあげて燃えさかっていた火の中から、突然、仙吉が全身の火の粉を振り払いながら、ものすごい形相で立ち上がり、権吉めがけてかぶさるように抱きついてきたのです。
権吉は、あんまりぶったまげてしまって、口から泡をふいてひっくり返っってしまいました。そばにいた銀蔵も、腰が抜けてしまって、まっ青になってがたがたふるえているばかりでしたそしてふたりともなにもわからなくなって、気を失ってしまいました。
翌朝早く、仙吉の骨を拾いにきた村人たちは、「あーっ」といったきり、ただぶるぶる震えながら、互いに顔を見合わせているばかりでした。それもそのはず、とうに骨になっているはずの仙吉と、火葬をいに行った権吉と銀蔵の三人が、その場にぬたばったまま、気絶しているではありませんか。
その後、権吉と銀蔵は、「(注2)もっけやみ」してふたりとも半年ばかりは、寝たきりであったということです。地元ではこの浜を「おじゃら小沙羅の浜」と呼んでいます。
注1 今の村長のこと
注2 しょっくで寝込んでしまうこと
「野ヶ島のかげ田」
野ヶ島の東の端に、陰田(掛田)という島があります。
昔は、この島にも数枚のたんぼがあって、陸続きになっていたのですが、数世紀にわたる浸食のために、離れ島になったといわれています。島は高さ20メートル余りの直立した姿をしており、別名「おいらん島」とも呼ばれて、名勝の一つになっています。
一年中いろいろの鳥が生息し、繁殖の絶好の場所でもあるので、大そう珍しい鳥も見られます。ことに「みさご」「たか」「むくどり」などの巣が、松の枝枝にたくさんあります。
昔、村の若者たちが集まって、みんなで「かけ」をしました。
「この島のてっぺんに、みさごの巣のある大木があっぺ。あの巣の中に、今ひなっこがいるんだとや。そのひなっこを生けどりにした者に、みんなで出し合って、田をけっこどにしたいが、みんなどうだや」
一人の若者がこういうと、みんな
「ああ、いがんべ。そいずはおもっしぇ」
と、賛成しました。
「ところで、誰が取っさいぐんだ」
ということになると、なにしろ島の頂上にはえている大木の枝だし、真下は絶壁で、波が岩に砕けている恐ろしい場所なので、しばらくはお互いに顔を見合わせているばかりで、進んでやろうとする若者はいませんでした。
そのとき、ひとりの若者が
「よしっ、おれがやっぺ」
といって、頭になべをかぶり、腰に太いなわを巻いて、絶壁をよじ上り始めました。
やっとのことで、頂上までたどり着いたのですが、今度は松の大木が待っていました。
若者は持って来た太いなわを、大木の枝にかけ、一枝一枝登って行き、とうとう「みさご」の巣に近づくことが出来ました。
さて、巣からひなをとろうとして、手を伸ばしたとたん、どこから飛んで来たのかものすごい羽音を立てて、親たか数十羽が襲いかかってきました。
若者は肝がつぶれるほどたまげて、あまりの恐ろしさに、ひなを取るどころのさわぎではありません。なんとか一刻も早く、木からおりて逃げようと思っても、手も足もしびれてどうしても動きません。全身からあぶら汗をたらしながら、真っ青になった若者は、一心に神様に祈りました。
「南無三宝、もろもろの神神さま。どうか無事に降ろさせたまえ。無事降りることが出来たら、一生餅を絶ちますから、どうぞ助けてください」
と、「願かけ」をしながら、一寸また一寸と、ようやくのことで地上に降りることができました。
その後、この若者は「一升餅」は食わなかったが、「二升餅」を食ったということです。
このときの「かけ賭」が、たんぼだったので、それ以後この島を、「かけ田」と呼ぶようになりました。のち、それがなまって「かげだ」というようになりました。
「鬼が浜の鬼征伐」
石浜には、鬼が浜、しるし首浜、かしら頭崎という地名が残っています。
昔、昔、鬼が浜(元の石浜小学校の下)に、毎夜のように鬼が現われて、畑を荒したり、女、子どもをいじめたりするので、島の人たちはたいへん恐れていました。
このままでは、島は鬼に占領されてしまうに違いないと思うと、気が気ではなく、村の人たちみんなが集まって、鬼退治の相談をすることになりました。
「こう毎晩毎晩、鬼に荒らされては、おっつけこの村はつぶれてしまうぞ。なんとかして鬼をやっつけでえもんだ。なにかええ方法はねえもんだべが」
みんなは、額を集めていろいろと相談しましたが、なかなか名案が浮かびません。そのうち誰いうとなく、「村の力自慢の若い者が、みんなで力を合わせて、鬼を征伐したらなじょだべなや」
と、いうことになり、元気のいい若者十数人を選んで、鬼退治の計画をしました。
若者たちは、夕方から畑の中に隠れていて、鬼が出て来るのを、息を殺して待っていました。日が沈んであたりがうす暗くなると、どこからともなく、ズシーン、ズシーンと地響きを立てながら、ものすごい赤鬼が目をぎらぎら光らせて出て来ました。あまりの恐ろしさに若者たちはふるえ上ってしまいました。
その中のひとりの勇敢な若者が、思い切って
「それっ、びくびくしねえで、やっつけろっ」
と叫びながら、飛びかかって行きました。
他の若者たちも、手に手に、くわや刀や、棒や竹を持って、三方から「わあっ」と取り囲み力の限り戦いました。そして、とうとう若者たちは、鬼を生けどりにしました。
村の人人が、こわごわ回りを取りまいて見ている中で、若者のひとりが刀を振り上げて、「えいっ」
とばかりに、鬼の首を切り落としました。
すると鬼の首は、地面に落ちないで、「壱の台」(現浦戸第二小学校)を飛び越え「首浜」まで飛んで行き、血しぶき上げながらどさりと落ちました。
それを見ていた村の人たちは、驚き恐れて真っ青になり、首浜まで走って行きました。
そして、この首を海水できれいに洗い清め、ねんごろに弔って、「頭崎」(今のかささき)に埋めたといい伝えられています。
現在では、頭崎の供養をする人もなくなってしまいましたが、このことがあってから後は、村人たちの鬼の供養は、長い間続いたということです。
「きつねのボッケ」
むかし、西町に三右衛門という百姓が住んでいました。三右衛門はおおひなた大日向に畑を作っていましたが、たびたび畑を荒されて困っていました。そのころは食べものも十分あった時なのでこれはきっときつねのしわざに違いないと思いました。そこで三右衛門は、このきつねをこらしめてやろうと、畑の小屋に泊って見張りをすることにしました。
「今夜もきっと、きつねの野郎がでてくっぺ。きたらば野郎、こっぴどい目にあわせてやっぞ」
三右衛門は、唐ぐわを握りしめて、目を皿のようにして見張っていました。
ところが、夜もだんだんふけて12時を過ぎたころ、とてもきれいなきつねの嫁入りが始まりました。三右衛門は、あまりの美しさにうっとりと見とれていましたが、ふと
「ははあ、これはおれがきつねに化かされているんだな」
と気がつきました。
「ギヤーッ」
という叫び声と同時に、嫁入り行列は消えてしまいました。そのとききつねが、なにか落として行つたようなので、そのあたりをさがして見ると、そこにきつねの「(注1)ボッケ」が落ちていました。三右衛門はそれをかぶって家に帰りました。
「ばばやばば、今帰ったど」
と声をかけると、
「ずんつぁんがあ、早がったなあ」
といいながら、ばあさんが戸をあけました。ところがそこには、花嫁姿の美しい娘さんが立っているではありませんか。ばあさんは、
「ずんつぁんは、どこにいんだべ」
と、きょろきょろあたりをさがすので、三右衛門ははっと気がつき、きつねのボッケを頭からはずしました。すると花嫁姿の娘さんが消えて、三右衛門の姿になりました。三右衛門は
「これはきつと、ボッケのせいだな」
と思い、今までのことをばあさんにくわしく話してきかせました。
三右衛門の家では、馬を飼っていました。毎日夕方になると、ローソクを立てて、馬に「(注2)すそ湯」をつかわせなければなりません。今夜もローソクを立てて、三右衛門がすそ湯をつかわせていると、馬小屋の前に人が立っています。
「三右衛門や、三右衛門。ボッケ返してけろ」
といいました。三右衛門は、
「ははあ、あのきつねのしわざだな」
と思ったので、
「なに、このつきしよ。人の畑を荒らすがってなにいうが。そんなにほすがったら、ボッケの代わりになにが珍らすいものを持ってこい。そすたらボッケば返してやっから」
といいました。
きつねは、次の晩一尺(30センチ)ばかりの棒を持ってきました。三右衛門は
「この野郎、こんな棒っきれ、なんだ。さっぱり珍らしぐもなんでもねえ。人をバカにすんな」
とどなると、きつねは
「三右衛門や、その棒を振って見ろ」
といいます。三右衛門はいわれたとおりに棒を振ると、パット光りが出て、あたりが明るくなりました。
「こえずはおもっせえ。あんべええもんだ」
三右衛門は喜んで、この棒ときつねのボッケをとりかえました。
三右衛門はしばらくの間、この棒の光で馬にすそ湯をつかわせていましたが、いつの間にかこの棒が消えてなくなっていました。三右衛門は、これもきつねのしわざに違いないと、うんとくやしがったということです。
注1 直径30センチ位いの丸い帽子のような毛のかたまり。
注2 馬のお尻などを湯で洗ってやること。
「尾島のごんぼ」
昔は、今の尾島町付近に谷地があり、大きな池のようになっていて、オオガイやボラなどがたくさんいました。そして付近の山には古ぎつねが住んでいて、よく人をだましたという話です。
ある冬の大そう寒い夜のことでした。池は吹きつける雪まじりの強い北風のために、カチンカチンに凍っていました。
そこへどこからともなく、大きなきつねが出てきて、
「まあずや、こったに・・すが張っては、魚が取れねえや。困ったな。なじょしたらよかんべえ」
といいながら、考え始めました。
「うん、うん、おらのしっぽで氷ばとかして、穴っこあけてやっぺ」
きつねは自分の太いしっぽで、氷をたたいたりこすったりして、とうとう穴をあけることが出来ました。
きつねは、得意そうに鼻をうごめかしながら、今度は太いしっぽをそろいそろりと穴の中にさしこんで、魚を取っては食べ、取っては食べていました。
そのうちに、寒さが一段ときびしくなって、氷の穴がだんだん小さくなり、とうとうしっぽが抜けなくなってしまいました。
きつねは・・・・・びっくらこい・て、いっしょうけんめいしっぽを抜こうとしましたが、びっしりと張りつめた氷につかまって、どうしてもとれません。
うんうんうなりながら、目を白黒させているところに、池の番人がやって来て、きつねを見つけてしまいました。
「あやぁー。氷の上さ大ぎつねがいるぞォ。この野郎だな。毎晩池の魚ば食い荒らしてだのはどうすっか見でろっ」
番人は、かんかんにおこって、太い丸太棒を持って氷の上を走って来ました。
きつえは、肝がつぶれるほどびっくり仰天して、なんとか逃げ出そうと大あばれ。とうとうしっぽを穴の中に残したまま、一目散に逃げて行きました。
氷の上には、まるで「ごぼう」のように太いしっぽが、によきっと立っていました。
それから人人は、このきつねを「尾島のごんぼ」と呼ぶようになりました。
むかし塩釜には、「湯壺のお夏」、「赤坂奴」、「尾島のごんぼ」のほかにも、「白坂ざほん」、「江尻七兵衛」、「女郎山おつる」などと呼ばれるきつねどもが、あばれまわって、人人を悩ませていたということです。
「ゆつぼ湯壺のお夏」
湯壺という所は、赤坂旧道にある地名です。昔ここは、仙台と塩釜を結ぶ重要な道路だったので、夜でも仙台まで鮮魚を運ぶ馬子の一群が、この道を通ったものでした。
この湯壺に「お夏」と呼ばれる古ぎつねがいて、勝手気ままな悪さをしては、馬子たちを悩ませていました。
馬子たちはお夏を恐れて、いつもここを通るとき、それぞれ魚を一匹づつ、
「お夏やあ、さあ、魚やるがらなあ」
と、大声で叫びながら、道ばたに放り投げては、お夏のごきげんをとっていました。
あるとき、こんなことを知らないひとりの馬子が、湯壺を通りかかったところ、道ばたに大きな魚が落ちているのを見つけました。
「なんとばかな野郎だ。どこのやつか知らねえが、大事な魚ば、こんなどごさ落どしてったぞ。んだ。この魚で酒っこでも飲むとすっぺ。ありがでえ、ありがでえ」
馬子は大喜びでその魚を拾い、自分の馬の背にのせて道を急ぎ、仙台の小田原あたりまでやってきました。
「さあて、このへんで、拾った魚でいっぺえやっか」
と、ひとりでにたにたしながら、馬の背を振り返って見た馬子は、腰が抜けるほどたまげてしまいました。
さっきまで馬の背に積んであった魚の荷が、拾った魚もろとも、それこそ・・・・さっぱど、一匹も残らず消えてなくなっていたのです。
それを聞いた人人は、
「これはきっと、お夏のしわざに違いねえ」
と、青くなったということです。
「赤坂やっこ奴」
昔、塩釜にあがつた魚は、必ず赤坂を通って、(注1)奏社の宮から原町に出て、原町で荷を積みかえ、仙台のさかなまち肴町に運んだものです。
この赤坂に「赤坂奴」と呼ばれる、古ぎつねが住んでいました。
あるとき、塩釜から魚を馬の背に積んだ馬子の一団が、赤坂にさしかかると
「下にィ、下にィ。下にィ、下にィ」
と、先ぶれの掛け声も勇ましく、向こうから殿様の行列がやってきました。馬子たちは、あわてて道の片すみに土下座して、行列をお迎えしました。
やがて、殿様の行列が通り過ぎたので、みな恐る恐る頭をあげ、さて馬を引いて出かけようとして、「あっ」とおどろきました。馬の背の魚は、すっかりなくなっているではありませんか。
馬子たちが土下座しているうちに、殿様の行列に化けたきつねが、ごっそり魚を持って行ったというわけです。
それから馬子たちは、このきつねを「赤坂奴」と呼んで、大そう恐れたということです。
注1 昔は「奏社」と書いたが、今は「総社」に統一している
「野ヶ島のこうしんひ庚申碑」
昔、野ヶ島に、樹令400年といわれ地上五尺(1.5メートル)ぐらいのところから、二またに分れた大きな松の木がありました。
この大木は、野ヶ島旧道の高台にうっそうと繁り、道をおおって、昼でさえも薄暗く、ひとりではとても通れないほど、薄気味の悪い場所でした。
この老松の枝に、毎夜大きな火の玉が出て、ぶらり、ぶらりと揺れているので、村人たちはとてもおっかなくて、この下の道を通る者はひとりもいなくなりました。
「なんだべなや。あのおっかねえ火の玉は」
「きっと化け物のしわざだべ。なんとかして、あの正体をたしかめたいもんだなや」
村人たちは、いろいろ相談した結果、力自慢の若者たちを選んで、火の玉の正体を見に行かせたのですが、その正体はどうしてもつきとめることが出来ませんでした。
村人たちは、
「これはきっと、なにかのたたりに違いねえ。みんなで供養してみたらどうだべなや」
ということになり、村人全員で盛んな供養をすることになりました。
そして、村の顔役の茂助ほか15人が世話人となり、「庚申碑」を老松の根元に建てました。その時から火の玉は出なくなりました。
毎年納めの庚申の日には、七色の菓子をこの日にそなえ、
「おこしんめえ、こおしんめえ。まいたり、まいたり、そわか」
と、繰り返し繰り返しおまじないを唱えて病難よけに講中の人たちが集まって、供養をしています。
碑の側面には「宝歴十庚辰年五月吉日」と刻まれています。
この庚申の老松も、明治44年の(注1)台湾坊主のために倒れて、今は根元だけになってしまいました。
注1 冬から春先きに吹く台風
「一つ目大人道の話」
昔、昔、寒風沢のはたけなか畠中というところに、おはつという女の子がいました。お父さんは舟乗りで、遠く江戸、浦賀、松前(北海道)の方まで航海していて、あまり家にいることはありませんでした。
ある晩いつものように、お母さんとふたりきりのさびしい晩ご飯を食べていると、お父さんがひょっこり帰って来ました。
あまり突然だったので、お母さんも、おはつも口もきけないでいると、お父さんは
「きようの夕方、わに鰐ヶふち渕さ入ったんだ。あしたの朝暗いうちに石巻さ舟ば回さねぐねえんだ。石巻で荷役すんだら、すぐにまた出て行くんだ。江戸から買ってきたおみやげが、おらひとりで持ちぎれねえほどあっから、船頭に暇もらってきたんだ。すぐにおれと一しょに鰐ヶ渕さ取りさいぐべ」
お母さんは大喜びで、お父さんといっしょに行くことになり、
「おはつや、おがさんはおどさんと、おみやげとっさ行ってくっから、おめえはひとりで、寝で待ってろ。鰐ヶ渕までは夜でもあっし、道も悪いがらな。わがったな」
と、いろいろなだめたり、すかしたりしてみましたが、今夜に限っておはつはひどく聞き分けがわるく、「おらも行ぐ、おらも行ぐ」
と、大声で泣きわめいてどうにもなりません。すると家の戸口でいらいらしながら待っていたお父さんは、今まで一度も見せたことのない恐ろしい顔をして、
「そんながき餓鬼は置いで、さつさどこいっ」
と、がみがみどなったので、お母さんは仕方なしにおはつをそのままにして、お父さんと出かけて行きました。
それでもおはつは泣きながら、お父さんとお母さんのあとを追って、ひこわだ彦和田の山の上り口まで行くと、お父さんが馳けもどってきて、
「この餓鬼、まだわかんねえのが。どうすっか見でろっ」
と、ものすごい顔でしかりつけました。その顔がなんとも恐ろしい形相なので、おはつはぎょっとして、立ちすくんでしまいました。
すると、お父さんの姿は、見る見る「一つ目の大人道に変わり、おはつに襲いかかってきました。おはつはあまりの恐ろしさに、ありったけの大声を張り上げて泣き叫びました。その声で近くの人人が、
「なんだ、なんだ」
と、家から飛び出して来ました。そしておはつをなだめて、わけをたずねました。
「これはきっと、きつねかむじなが、おがさんをだましたのにちがいねえ」
と、村中にふれて、あっちこっち手分けしてさがしましたが、とうとうその晩はお母さんのゆくえはわかりませんでした。
その日鰐ヶ渕に入った舟は、一隻もなかったということです。
あくる日も、朝早くから村の人たち総がかりで、鐘や太鼓、金だらいなどを打ち鳴らして、島中くまなくさがし回りましたが、お母さんはどこにも見つかりませんでした。
一方、舟で海岸をさがしていた人たちが、つきだて築建山の南の崖下に、おぼれて死んでいるお母さんを見つけました。
着物には獣の毛が、いっぱい着いていたのでやっぱりこれは、古むじなのしわざだろうと、みんな恐ろしがって語りあったということです。
「清太郎のいかり錨上げ」
寒風沢港の全盛時代には、毎日浦戸の島島に、風待ちしている(注1)藩米輸送の千石船が見られました。それらの船の乗組員は、地元出身の若者たちが多かったそうです。
船が停泊するときは、とうびょう投錨といかり錨上げが、船員にとって大仕事でした。どの船にも(注2)カグラサンがあって、数人がかりで作業しましたが、なかなか大変な仕事で、かなり時間がかかりました。
錨上げの最中(注3)はやてに疾風が吹いて、岸に打ち上げられたり、積荷もろとも難破したりすることもたびたびありました。
ある日、(注4)イナサの悪天候のため、(注5)マガカリ中だった乗組員のなん人かは、自宅で待機しており、船には独身者と幹部船員が数人だけ残っていました。
ところが、天候が予想より早く(注6)ダシ風になり急速に回復してきて、潮流の条件もよくなっていっときも早く船を出さなければならなくなりました。
けれども、肝心の錨上げの船員がおりません。船頭は気が気でなく、顔を真っ赤にして、
「早く、早く船を出せっ。まごまごしてっと、船が出せねぐなっとォ」
と、大声でどなるばかりでした。
その時、船に残っていた清太郎という船員が、とび出してきました。
「船頭さぁ。おらひとりで錨上げっから、船ば出さえん。大丈夫だから」
と叫けぶと、「えーいっ」と掛け声も勇ましく、綱に手をかけると、軽軽と船の上に錨を引き上げました。
清太郎の怪力のおかげで、船はらくらくと出航し、約束の日までに、米を倉庫に運ぶことが出来たということです。
当時、千石船の錨はよつ又で、30貫(120キロ)から50貫(200キロ)も目方があったといわれています。
注1 木で作った巻上機
注2 幕府の直轄領から江戸御蔵に納入されるこうまい貢米(ごじょうまい御城米)と、ほんごくまい本石米といわれて有名だった仙台米の輸送のこと
注3 急にはげしく吹き起る暴風雨
注4 東風、コチ
注5 停泊
注6 北西の微風
「力だめしの話」
野ヶ島の熊野神社の、最初に作られた鐘には、神社の由来が刻まれてあったそうですが、それは幕末のころに微発されてしまいました。
明治初年に、再び鐘を作って神社に奉納することになり、山形の鐘作りに注文したのが出来上がったので、馬車二頭引きで(注1)高城村までやって来ました。そこから野ヶ島までは村人たち総がかりで、舟数隻をつなぎ、海上を運ぶことにしました。大変な仕事でしたが、それでも一日がかりで、部落のかし河岸に到着しました。
今度は、神社までの道を太い棒に鐘をつるして、それをかつぐ者、綱で引っ張る者、村人たちは大騒ぎでした。
なんとかかんとか、鐘を鐘つき堂に納め、さてそれからは村中そろってのお祝いになりました。みき神酒を汲みかわし、歌やら踊りやら、大にぎわいになりました。
そのうちに、それぞれ自慢話に花が咲き、いっそう騒騒しくなりましたが、そのうちひとりの年寄りが
「みなの衆や、あのつるした鐘をな、ひとりでもちゃげた者には村の仕事を免除するごどにしたらどうだべ」
と、村の人たちに座興の力だめしを持ち出しました。
「そいずは、おもっしぇ。やっぺ、やっぺ」
ということになって、若者たちが代わる代わる出ては、顔を真っ赤にしてためしてみましたが、鐘はびくとも動きませんでした。
そのとき、庄右衛門という若者が進み出て、
「おらがやってみっぺや、ちょっくら、どいてけさえん」
といって、つるした鐘の中に上半身を入れて、鐘の下輪を両腕でささえ、
「ええやあっ、ううん」
と、ものすごい掛け声をかけて持ち上げました。鐘は見事に高高と上がりました。それから庄右衛門は、その鐘をつり下げたかぎからはずして、頭にかぶって、猫神様(熊野神社北方100メートル)の坂を下り、かし河岸通りを一周して、熊野神社の坂を登り、鐘をもと通り鐘つき堂に納めたということです。
庄右衛門の家では、このために一年になん回となく、村の仕事を無報酬ですることを、数年間免除されたそうです。
この鐘も太平洋戦争のとき、微発されてしまって今はありません。
注1 今の松島町
「うちみちょうじゃ内海長者の話」
今から290年ほど前のことです。仙台の殿様で、伊達吉村という人が、まだ子どものころ松島の天童庵で学問の修行をしていました。
ある日、若様は勉強にあきたので、たったひとりで舟遊びをしていました。ところがにわかに大風が吹き出し、若様の乗った小舟は、沖へ沖へと流されてしまいました。しかも、風はますます強くなり、波がさかまき、小舟は今にも転覆しそうでした。こうして若様の舟は、浦戸の野ヶ島の近くまで流されて行きました。
島の人たちは、子どもがひとりだけ乗った小舟を見つけましたが、ただ「あれよ、あれよ」と叫ぶばかりで、どうすることも出来ませんでした。
そのうちに、若様の乗った小舟は、島の長者屋敷の前にある、「ひらね平根」(亀の小石とも呼ばれる)に乗り上げました。
村人たちは、さっそく子どもを助けようと小舟に近づきましたが、その子どもが、あまりに立派な着物を着ているので、びっくりしました。しかも着物についている紋章が「(注1)竹にすずめ」の紋なので、大騒ぎになりました。
「ややっ。あれは藩主さまの紋でねえか」
「なにっ。藩主さまの紋だって。あっ、んだ、んだ。ほんとに藩主さまの紋だどっ」
村人たちは、さっそく島の内海長者にこのことを知らせました。
長者は、倉から米俵を運び出し、これを次次に海に投げ入れて、さん橋を作り、若様を渡らせようとしました。しかし若様は、その俵を踏まないで腰まで海水につかりながら、ようやく陸にはい上りました。
若様は島の観音堂にお参りし、無事を報告しました。そのあと長者の家に来て休み、翌日迎えにきた家臣たちに付添われて、松島にお帰りになりました。
それからなん年かして、若様が藩主になりました。ところがその年大ぜいの役人たちが、内海長者の家にやって来て、家も財産も全部没収してしまったということです。
注1 藩主伊達家の紋
「猫神様の話」
昔、うわて上手の家に、三毛のとっしょり猫がいました。ある晩、ひとりのぎだゆう義太夫かたりが村にやってきて、自慢の義太夫を聞かせることになったので、日頃あまり楽しみのない村人たちは大喜びで、そろって義太夫を聞きに行きました。
上手の家には、ばあさんがひとり残って、炉ばたでキセルでタバコを吸ったり、お茶をのんだりして留守番をしていました。
すると、炉ばたの向う側に、三毛のとっしょり猫がきて、のどをごろごろ鳴らしていましたが、突然ばあさんに
「ばんつぁんや、ばんつぁんや。今までずい分長い間世話んなったがら、お礼に今夜は、おれがばんつぁんに義太夫きかせっぺな」
といいました。
ばあさんは、うす気味悪かったが
「んだな。三毛は義太夫なんて、知ってんのがや」
ときいたら、
「今な、隣りさ行って聞いてきて、おぼえたんだ。ただな、ばんつぁん、約束がひとつあんだが守ってけらえんよ。ほかの人さどんなことがあっても、話さねえでけらえん。もしもこのことをばんつぁんが人さ語ったら、おれは生きてられなくなんだがらね」
と、ばあさんに固く念を押しました。
ばあさんは、ますますうす気味悪くなりましたが、仕方なく
「わがりした。約束はきっと守っから、きかせでけらえん」
といって、猫の義太夫を聞くことになりました。三毛猫は、いろいろと顔や身振りをまぜながら、(注1)つぼざかれいげんき壺坂霊現記の一節を、声を張り上げ、節回しもおもしろく語りはじめました。
しばらくして、戸口にがやがやと大勢の人の声がすると、三毛猫は義太夫をぴたりとやめて、炉ばたで知らぬ顔をしていました。
ばあさんが、みんなの話を聞いて見ると、猫の語った義太夫と全く同じでした。
次の日、ばあさんは三毛との昨夜の約束をうっかり忘れて、
「ゆんべの義太夫はこうだったべ。おらはな、三毛にすっかり聞かせらったど。おもせがったなあ」
と、いってしまいました。
炉ばたでうずくまっていた三毛は、うらめしそうな目をして、ばあさんを見ていましたが、急に外にとび出して行きました。
なん日たっても帰って来ないので、みんなでさがしたところ、裏山で死んでいるのが見つかりました。
ばあさんは、三毛との約束を破ったことを心からわびて、家の裏にほこら祠を建てて、猫の霊をまつり、家の氏神様として毎年手厚く祭りをしたということです。
注1 じょうるり浄瑠璃の名曲で、普通は「壺坂」といわれかぶき歌舞伎でも上演されている。
「すばり地蔵」
さぶさわ寒風沢のひよりやま日和山に、「すばり地蔵」と呼ばれる石ぼとけがあります。
その昔、寒風沢港がとても栄えていたころ、この港の女たちが、恋人が出航するのを止めるため、この石ぼとけを荒なわで縛って祈願しました。
そのころ、ある料理屋に「さめ」という、きりょうのよい女がいました。彼女は、愛し合っている若者が遠く船出するのを悲しみ、船を一日でも引き止めたい一念から、日和山に登りました。そしてこの石ぼとけを荒なわで縛り、
「船を引き止めて下さい。引き止めたら解いてあげます」
と、がん願をかけました。すると、その夜から翌日にかけて暴風雨となり、船は出られなくなりました。
それ以来、この石ぼとけは、女たちによって、ときどき縛られるようになりました。
縛ったまま朽ちたらしいなわが、そのひざにずり落ちているのは、がん願がかなえられたうれしさに、ほどくのを忘れたためか、それとも女の思いがかなえられず、そのままになっているのでしょう。
今では縛られることもないままに、静かに林の中に坐りつづけています。
「へび草の話」
ずうと昔、牛生に、じいさんとばあさんがいました。じいさんは「新蔵」といいました。ふたりには子どもがないので、いろいろの生きものを飼って、かわいがっていました。その中には「まむし」もいました。
ある日のことです。急に雨が降って来たので、じいさんとばあさんは、急いで庭に干していたまぐさ馬草をなや納屋に入れはじめました。ところが、ちょうどその時、ほしぐさ干草の中で眠っていたまむしを、うっかりして踏みつけてしまいました。
びっくりしたまむしは、思わずばあさんにかみつきました。
「おらが、こんなにめんこがっているのに、かぶづくなんて、なんてえらすぐねえんだべ」
と、じいさんとばあさんは大そう悲しみました。
まむしにかまれたばあさんの傷口は、いっこうによくなりません。
そんなある日のこと、このまむしがどこからともなく、一本の草をくわえて来ると、じいさんのからだに巻きついて来ました。じいさんもばあさんも、はじめは、へびがなんでそんなことをするのかわかりませんでしたが、
「ははあ、この草を傷口につけろというんだな」
と気がつき、その草をせんじて傷口につけると、不思議なことに一ぺんになおってしまいました。
じいさんとばあさんは大変喜んで、このまむしを前よりもいっそうかわいがりました。
へびがくわえてきた草は、代代じいさんとばあさんの家で「へび草」と呼んで、へびにかまれた時のクスリとして、大切に伝えられてきました。
これが牛生の「まむし湯」の起こりだといわれています。
またこの付近の山にはいる時、
「牛生の新蔵、家内の者」
と唱えると、まむしにかまれなかったといわれていますが、今では、こう唱えて山にはいる者は、いなくなったということです。
「母子石の話」
塩釜の母子沢に「母子石」という石があります。昔多賀城を築いた頃のことです。城作りのお役人が自分の妻にするよい娘はいないかと、あちこちさがしていました。
石堂に立派な長者が住んでおり、その娘がよかろうと人を頼んで、いろいろと申し入れましたが、親子ともどうしても承知しませんでした。
そのうちに、城もどんどん工事がはかどり、もはや完成という時になって、誰いうとなく、「こんな立派なお城だから、人柱を立てて永久の守りにしなければならない」
ということになって、それから誰かれと人選びが始まりました。
「このあたりで、立派な人ということになれば、石堂に住むあの人しかいない」
というみんなの意見で、とうとう娘の父が人柱に立つことにきまりました。
娘は、こんなことになったのも、自分がお役人のところにお嫁に行くのを断ったためだろうと思い、
「私はどんな難儀でも我慢するから、どうかお役人に、お嫁にやって下さい」
と、涙ながらに願いましたが、父は
「お前がお役人のところに嫁に行けば、私は助かるかもしれないが、誰かが人柱に立たなければならない。私の代わりに迷惑する人が出るのだから、とてもそんなことは出来ない」
と、ついに人柱に立つことになりました。
母と娘の嘆きようは、なんとも言葉でいいあらわせないほどでした。
父が人柱に立つ時刻になると、母と娘はお城の方角を向いて両手を合わせ、一心に祈って泣き悲しんでいました。
哀れなことに、母と娘のふたりは悲しみのあまり、いつの間にか冷たくなって死んでいました。
母子の立っていた石には、ふたりの足型が残されています。
注 母子石については、このほかにいろいろの伝承があります。
「弁之助の話」
昔、文政年中のこと、野ヶ島に弁之助という人が住んでいました。気立てがよく正直者でしたが、村の人たちはいつも弁之助のことを、「べの弁之」と呼んでばかにしていました。
お父さんは早く亡くなり、お母さんとふたりで暮らしていました。お母さんは、弁之助にも何か暮らしの助けをしてもらおうと考えた末、焼きもちを作って、毎日さぶさわ寒風沢港や、宮戸村あたりまであきないをさせることにしました。
弁之助は、お母さんのいうことをよく聞いて、いっしようけんめいあきないに精を出して働きました。
みんなは、正直者の弁之助をかわいそうに思って、よく焼きもちを買ってくれましたが、ときどきからかって
「べの弁之、その焼きもちなんぼだ」
ときくと、
「にもん二文」
と答えます。
「どうだ、三文にまけねえが」
というと、
「やんだ、やんだ」
とむきになって首を振りました。二文より三文の方が値うちがあることなど、弁之助にはわからないから、ただもうお母さんのいいつけ通り、二文以外には絶対に売らなかったのです。
そのころ浦戸から、たかぎ高城や塩釜へ、村役人の往復とか、書状を届けるのに舟を出しました。
これを「おふなぶ舟夫」といい、村中が順番でふたりか三人、時にはひとりでその使いにあたることがありました。
ある時、弁之助にもその順番が回って来て、ひとり舟で塩釜へ使いに出かけました。
さて用事がすんで、塩釜からの帰りのことです。折りから西南の順風で、帆を上げて航海すれば、ちょっとの間に、野ヶ島に帰れるというよいひよりでした。
ところが弁之助は、そんなことにさっぱり頭が回らないから、帆道具一切を用意していながら、せっせとろをこいで島にもどってきました。それを見た村の人が、
「べの弁之や、こういう風んどぎは、帆を張って来るもんだど」
と教えました。
その後また弁之助は、お舟夫の番で塩釜へ行きました。この時は強い東風が吹いていて、野ヶ島までもどるにはまるっきり逆風で、帆を使えない状態でした。弁之助は困ってしまいました。
「この前のもどりには、帆を使えと教えらったが、こんではどうにも帆ばかけらんねえ。ほんでも、まだろをこいで帰っと、笑われっしなじょしたもんだべ」
弁之助は、いろいろ考えた末、まず塩釜から大塚浜(桃生郡)までろでこぎ上り、そこからは高高と帆を張って、いっきに強い東風にのり、得意満面で島に帰って来たそうです。
また、こんな話もあります。
弁之助が、かじを取り、たばこを吸っていた時のことです。舟べりでぽんと吸いがらをたたいた拍子に、キセルのがん首を海の中に落してしまいました。弁之助はなたを持って来て、いま吸いがらをたたいた舟べりの所に、傷をつけはじめました。
「あぶねえ、かじを離すと、舟ひっくりがえっど」
「なんでまた、そんな所さ傷などつけてんのや」
弁之助はまじめくさった顔で、平然とこう答えました。
「野ヶ島さ着いだら、この傷の下の海から、がん首ばさがすのっしゃ」
船が野ヶ島に着くと、弁之助はさっそく海に飛び込んで、舟べりの傷の下の海を、しきりにさがし始めました。
みんなどんなに話して聞かせても、絶対にこの下にがん首があるはずだといって、へとへとになるまでさがしつづけました。
今でも、このようなばかげたことを、浦戸地方では、
「べのばし弁之走り、べの弁之さがし」
といって、愚かな仕事のことを意味する言葉になっています。
「長者の朝飯がひる蛭」
昔、野ヶ島に、だいだい代代、うちみ内海さえもんのじよう左衛門尉と名乗る長者が住んでいました。大船を四十そうあまり持っていて、これを「いろは船」とよひ、諸国に航海して手広くあきないをしていました。
何代目かの主人で、大そう朝寝の好きな人がいました。いつも人人が、せっせと働いている頃にやっと起き出して来て、ゆっくりと朝飯を食べるという暮らしを続けていました。
ところが、ある日のことです。いつものようにゆっくりと起きて、朝飯を食べようとすると、手にした茶わんの中に、気味の悪い蛭がうじゃうじゃいるではありませんか。長者は青くなって、給仕をしていた下女に茶わんを投げつけて、
「ばかもの、こんな飯が食えるかっ」
とどなって、またふとんをかぶって寝てしまいました。下女は頭から白い飯粒をあびて、ぽかんと口をあけていました。
長者は、とうとうその日は、夕飯も食べませんでした。翌日もまた朝飯が蛭に見えて、どうしても食べられませんでした。
こんなことが毎日毎日続くので、長者は、今度は昼まで寝ていて、昼飯から食べることにしました。ところがそのうち昼飯もだんだん蛭に見えてきて、食べられなくなりました。
そこで長者は、一日中寝ていて夕方に起き出し、夕飯から食うことにしました。ところが夕食もだんだん蛭に見えて来て、とうとう三食とも食えなくなってしまいました。
長者は、ありあまるほどの富を持っていながら、何ひとつ食うことが出来ないで、飢え死にしてしまいました。
これについては、こんなうたが残っています。
朝寝する子は、(注1)無限の鐘よ 朝のまんま飯が蛭(昼)になる。
注1 無限地獄におちる鐘のこと
「古むじなの話」
昔、昔、鯨島に古むじながいました。
ある晩のことです。ほお朴島の人が鯨島の近くに、はも釣りに出かけました。すると鯨島からにぎやかな鼓の音が聞えてきました。
漁師は驚いて、ぽかんと口をあけて鼓の音を聞いていると、急に自分の名前を呼ぶものがあります。ぎょっとしてあたりを見回しましたが、どこにも人影はありません。
「今夜は、おめえさ、やしま屋島のかつせん合戦のじょうるり浄瑠璃ば聞かせっから、よっく聞いでろ」
というと、またにぎやかな鼓の音がして、浄瑠璃を語りはじめました。漁師はそれがあまりいい声なので、恐ろしいのも忘れてうっとり聞きほれていました。
しばらくしてから、
「あとの段は、あしたの晩聞かせっからまた来いよ」
といって、それっきり何も聞えなくなりました。漁師は次の日、そのことをみんなに話して、その晩は大勢で鯨島に出かけました。
ところがどうしたわけか、いくら待っても、鼓の音も、浄瑠璃も、全然聞えてきません。せっかく楽しみに出かけて来た人たちは、がっかりして家に帰ってしまいました。
「不思議なごども、あるもんだなや」
と思って、その漁師は次の晩に、今度はひとりで鯨島に夜釣りに行きました。
そうすると、また鼓の音がして、浄瑠璃を語り出し、夜が明けるまで聞かせられました。
それからというもの、たったひとりで鯨島に夜釣りに行った人は、みな浄瑠璃を聞かせられたということです。
「大根明神とハカリ松」
浦戸の島島の、はるか沖あいの海岸に、「(注1)大根明神」と呼ばれる大岩礁があります。海底に出来た山のようなものですが、頭を海面に出していないので、船でいっても、どこに岩礁があるのか見ることは出来ません。
ところが大根の回りには、たくさんの魚が集まるので、沿岸の漁師たちはみんなここをよい漁場にしています。
今のように、海図や、コンパスがあれば、すぐに大根の位置を正確にとらえることが出来ますが、こういうものがなかった時代や、また持っていない小舟はどのようにして大根に行くことが出来たのでしょう。
この大根を十分に利用するには、「山ハカリ」とか「森ハカリ」によって、正確な位置をおさえたのです。つまり、海上から陸地に見える高い山とか、目印になる高い木を見通し、経緯を合わせるようにして、その地点に舟をとめるのです。このようにして漁師たちは、大根の位置、岩礁の高低、そして魚群の集まる地点まではかり、漁をしていたのです。
大根のハカリに利用されているのが、野ヶ島観音堂の松の大木と、野ヶ島の南端にある陰田島なのです。観音堂の老松は、樹令6-700年といわれ、大根漁場の「ハカリ松」として、今でも欠くことの出来ない重要な役目を果しています。残念ながら昭和41年6月に、この「ハカリ松」に落雷があり、それから年年枯れてきたということです。
また、野ヶ島の本屋敷に、熊野神社の旧台座石があり、ここに上ると観音堂の老松と陰田島を結ぶ直線上の南方に、大根明神があります。島の人人は、昔からこの台座に上り、海上安全と大漁の祈願をしています。
注一 花渕みさきの海上7キロの沖合いの海底にあり、南北2.5キロ、東西2.5キロの大岩礁です。鼻節神社は、もとここにあったのですが、貞観(859年—876年)の大地震で陥没したので、現在の地に遷宮されたと伝えられています。
この大根岩礁付近は一大漁場で、こんぶ、あわび鮑の宝庫でありました。このこんぶ、鮑は「陸奥のこんぶ、花渕の鮑」として、国府、藩主えの献上品としても有名でした。
「釜の淵」
昔、塩釜を舟で出て、ししざき獅子崎を左に回って行くと、釜の渕という深い底なしの渕がありました。
おお昔、しおつちのおきなのかみ塩土老翁神が塩をたいたという釜が5個、御釜神社の宝物として祭られていました。ところがある年のこと、ひとりの盗人がその中の一個を盗んで舟に乗って沖へこぎ出しました。
ちようど釜の渕にさしかかった時、突然見上げるような大波が起こり、進退きわまって、とうとう人も舟も釜もろとも海底深く沈んでしまいました。そしてここは底なしの渕になったのです。舟でそこを通る者は、ぞっと寒けを感じるほどだったということです。
8月5日の御釜神社の祭典には、この渕から海水をくんで来て、御釜のお水替をしていました。
「おしょうと小僧の話」
むかし、むかし、ある寺におしょうさんと小僧が住んでいました。おしょうさんは夜になると小僧に
「お前は朝早く起きて掃除するんだがら、早く寝ろ、早く寝ろ」
といって、むりやり寝かせました。
おしょうさんは、小僧の眠ったころを見はからって、そっと大福餅を戸だなから出し、炉ばたでひとりでお茶をのみながら、「ホド(注一)」でほどよく焼くのでした。餅が焼けると、おしょうさんはニヤニヤしながら、火ばしで拾っては、うまそうに食べました。
ある晩小僧は、いつものように早く寝かされましたが、目がさえていっこうに眠れません。なんべんも寝返りを打っていましたが、ますます目がさえるばかりでした。小僧は仕方なくお経の暗唱をはじめました。
すると隣のへやから、とてもいいにおいがしてきました。小僧はごくりとつばをのみながら、そっと起きて、ふすまのすき間からのぞいてみると、おしょうさんは火ばしで、ホドの中をかきまわしながら、焼けた餅の灰を払い、ひとりでニヤニヤしながら、こっそりうまそうに食べるのでした。
小僧は、
「おれも、あの大福をくでえもんだ。なんとかええくふうがあんめえがな」
と、いろいろ考えました。
「おしょうさん、おしょうさん」
と大きな声で呼びました。おしょうさんはびっくりしましたが、そしらぬ顔で
「なんだ。まだ寝ねえのが」
といったので、小僧は待ってましたとばかり、おしょうさんのそばに行きました。
「おしょうさん、わせったげっど、孫作の家で、あした早くおがむさ来てけらえんとっしゃ」
おしょうさんは、とぼけたふりをして
「孫作ってどごだや」
とききました。小僧は火ばしをとって、ホドの中をぐるぐるかき回し、
「おしょうさん、ここが地蔵さんで、ここを左さえぐと田子作家で、そこを右さ曲がっとすげばんつぁんどごだ」
と、餅を全部掘り出してしまいました。そして最後に、
「孫作の家は、こごっしゃ」
といいました。おしょうさんは、
「なんだ、ここはおらのお寺だべっちゃ、やあや、おめえには負けだなや」
と、苦笑いしながら半分分けして食べました。それからおしょうさんは、なんでも小僧と分けて食べるようになったということです。
孫作というのは、小僧のわんぱく仲間の名前でした。
注一 炉端の火をたく中心部
「スワッピリな婆さんの話」
むかし、浦戸のある島に、とてもスワッピリな婆さんと、ひとり息子が住んでいました。
婆さんは、毎日爪をほうきのようにして、こつこつと働きながら、ひとり息子を育ててきました。そのうちに、息子もだんだん大きくなり、一人前の若者になったので、婆さんは嫁さがしをすることになりました。
ところが婆さんの嫁とりの条件は、
働き者であること
きりょうよしであること
小食であること
と、いうことでありました。
婆さんは息子となん日も話し合って、こういう娘さんをさがすことにしました。あっちの村こっちの村と尋ねて歩きましたが、なかなか見つけることが出来ませんでした。
こうして、一年ばかり過ぎたころ、婆さんはついに遠くの島で、自分の気にいった嫁を見つけることが出来ました。
「息子や、喜んでけろ、とうとうええ嫁ごを見つけてきたど」
婆さんはとても得意そうでした。
いかにも嫁は、働き者であいきょうもよく、縫い物もでき、隣近所の評判もよい上に、ご飯も一粒か二粒しか食べませんでした。婆さんは大喜びで、
「嫁や、嫁や」
と、大そうかわいがりました。
ところがある晩のこと、婆さんが便所に起きると、台所に灯がついていました。
「なんだべなや。こんな夜中に、台所にだれがいるんだべが」
と、ひとり言をいいながら、戸のすき間からそおっとのぞいて見ました。
婆さんはとたんに腰が抜けて口もきけなくなり、真っ青になってガタガタふるえるばかりでした。
嫁は、自分の髪の毛をかき分けて、頭のてっぺんの大きな口に、釜の飯を大べらでしゃくりこんでいました。
婆さんは、それから一生、立つことも、歩くこともできなくなったということです。
「九ノ吉とむじなばやし」
浦戸の無人島で一番大きな島は、大森島で、昔からきつねやむじなが住んでいました。
昔この島に、九ノ吉という漁師がいました。
毎晩夜づりに大森島あたりまで出かけていました。
ある晩、思いがけないほどの漁があったので、夜もふけたことだし、今夜はこのぐらいにして終わりにしようと、帰りじたくを始めました。
すると、すぐ向かい岸に、あかりが一面に見えてきました。その明るいことといったら、まるで昼間のようでした。
手をたたく者、大声で笑いさざめく声、笛や太鼓のにぎやかなはやしなど、大変な騒ぎが聞こえてくるのです。
「なんだべなや。あのお祭りみてえなのは。おらぁ、今まで見たことも聞いたこともねえ。不思議なこともあるもんだなや」
九ノ吉は、少しばかり不安に思いながら、それでもそっと舟を岸べにこぎよせていきました。
見ると、岸の舞台では、色とりどりのはなやかな衣装をつけた美しい女たちが、歌やはやしに合わせて、おどりのまっ最中でした。
九ノ吉は、おっかないのも忘れて、このにぎやかな踊りに、うっとりとして見とれていました。
しばらくすると、きれいに着飾った女たちがやってきて、
「よく来て下さいました。なにもありませんが、どうぞお上がり下さい。ゆっくり踊りを見て行って下さい」
と、親切に座敷に案内され、酒や魚と珍しいごちそうが、たくさん出され、大振舞をうけました。九ノ吉はすっかりいい気持ちになって、そのままぐっすり寝込んでしまいました。
九ノ吉が眠りからさめたのは、もう東の空がほのぼのと明るくなるころでした。
九ノ吉は、頭がぼうっとして、何がなんだかわからず、まるで夢の中にいるようでした。
ところが、舟の中を見ていっぺんに目がさめてしまいました。昨夜釣った魚が、どこえ行ってしまったのか一匹もいなくなっていたのです。
ただ板の間には、たくさんの足跡と、たぬきの毛が残っているだけで、大森島の海岸はいつもの様子と少しも変わっていませんでした。
「小夜姫の哀話」
昔、昔、いくさに破れたひとりの武将が、海を渡って大島(現在の寒風沢)に落ち延びて来ました。
それからなん年かたったころ、小夜姫という身分の高い美しい姫が、大島にやって来ました。小夜姫はこの武将の妻でしたが、やっとさがしあてた時は、もう夫の武将はこの世を去ってしまっておりました。
小夜姫は大そう悲しんで、夫の墓の近くに小さな庵(いおり)を建て、朝夕夫のめい福を祈って、静かに暮らしておりました。
この北のみさきの角を、寺崎といい、入り海を「美女(びんじゃ)ヶ浦」と呼ぶようになったと、伝えられております。
また、南の太平洋に面したところに、本屋敷(もとやしき)という所があり、その昔観音堂が建っていたので、観音崎といわれ、行基の作といわれた聖観音のお像がまつられていたといわれています。
(今は松林寺に安置されています)
小夜姫は、この観音像を深く信仰し、尼になると毎日毎日ただ一心に念仏を唱えて、夫の供養をしておりました。
村人たちは、観音様のように美しく、気高い小夜姫のために、代る代るお供えものを持っては、姫を慰めておりました。
こうして幾年か過ぎたある日、十才ぐらいのふたりの姉妹が、遠い都から、はるばる大島を尋ねて来ました。それは小夜姫の娘たちでした。
「お母さま、お母さま」
ふたりの幼い娘たちは、ただ母にすがって泣くばかりでした。
小夜姫は、娘たちを固く固く抱きしめて、
「よくお母さまのところがわかりましたね。かわいそうに、かわいそうに。どんなにつらかったでしように」
と、心からふたりをいたわりました。母と子は手に手を取って、いつまでもうれし涙にくれておりました。
やがて、小夜姫は思いなおすと、心を鬼にして娘たちにこういいました。
「お母さんは、もう国に帰ることは出来ないのです。お父さまのお墓を守って一生ここで暮らします。あなた方は国に帰って、立派に成長して家名を立てるようにして下さい」
と、なんどもなんどもいい聞かせました。
幼いふたりの娘たちは、
「いやだ、いやだ。いつまでもお母さまといっしょに暮らします。どうかここに置いて下さい」
と、小夜姫にすがりついて泣き叫びました。
小夜姫は身を切られるほどつらい思いでしたが、娘たちにはどうしても国に帰って、立派に家を再興してもらわないと、亡くなった夫に申し訳がないと思いました。娘たちがここから出て行くためには、自分がこの世を去るほかにはないと決心して、鰐ヶ渕の断がいから、青い深い渕に身を投げて死んでしまいました。
村人たちは、小夜姫はこの渕にすむ大鰐鮫(わにざめ)に食われて、再び浮かんでこなかったと語り伝えています。
残されたふたりの幼い姉妹は、途方に暮れて、幾日も幾日も父の墓の前に泣きくずれておりましたが、ある日村人たちが来て見ると、ふたりの姉妹は、固く抱き合ったまま冷たくなっていたということです。
寺崎の向かい側に、二つの小島があり、一晩中
「小夜恋し、母恋し」
と鳴く鳥がいたということです。それはこの哀れな姉妹が鳥になって、毎晩毎晩鳴くのだと、島の人たちは語り伝えております。
大きな方の島を「大夜鳥(おおよどり)島」、小さい方の島を「小夜鳥(さよどり)島」と呼んでいます。
「石浜の雨降り石」
石浜の津森山の山頂に、大きな石があり、土地の人人はこの石を、「雨降り石」と呼んでいます。
昔、少し日照りが続くと、村のたんぼも畑も、からからに干上がって、飲み水もなくなってしまいました。
そこで村の人たちは、雨ごいすることにしました。みんな津森山に集まって、かがり火をたき、石を取り囲んでぐるぐる回りながら、
「雨、雨、降れェ降れェ。沖にかんだち(注一)、つったったァ」
と、繰り返し繰り返し、雨ごいの祈りを唱えながら石をたたきました。
すると、今までからっと晴れ渡っていた大空に、急に黒い雲がむくむくとわき出して、真っ暗になったかと思うと、ざあっと滝のように雨が降って来ました。村の人たちは飛び上がって喜びました。
このことを伝え聞いた松島、利府、七ヶ浜の人たちは、干ばつになると大勢で石浜にやって来ては、「雨降り石」をたたいて、雨ごいをしたということです。
また、昔この土地に「相州雨降岩尊大権現」(そうしゅうあめふりいわのみことだいごんげん)を祭ったともいい伝えられています。
注一 神立と書き、方言で夕立のこと
出版:塩竈市教育委員会
材質・形状:冊子