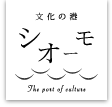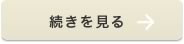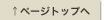詳細分類の一覧
絵馬「鮭を運ぶアイヌ」
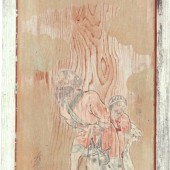
塩竈市指定・有形民俗文化財 寒風沢島の神明社に奉納されていたこの絵馬は、 親子と思われる二人のアイヌが鮭を持ち運ぶ姿を描いたもので、 大きさは縦140㎝、 横68㎝。 絵の左側に 「藤原高次」 の名前と花押があります。 … 続きを読む
銅鉄合製燈籠:文化燈籠 A lantern made of copper and iron: Bunka lantern

銅鉄合製燈籠:文化燈籠(どうてつごうせいとうろう:ぶんかとうろう) 塩竈市指定・有形文化財 伊達家九代藩主周宗が幕命により蝦夷地警備に出役、 無事任務遂行を感謝して文化6年 (1809年) に、 銅鉄合製の精巧な花鳥、 … 続きを読む
太刀銘雲生 Unsho Sword

太刀銘雲生(たちめいうんしょう) 国指定・重要文化財 鎌倉末の作品、 長さ三尺四分 (92.1㎝)。 反りの高い長寸の勇壮豪快な太刀です。 古来より鹽竈神社例祭御出幣式の威儀御太刀として伝わっています。 鹽竈神社右宮一禰 … 続きを読む
算額 Sangaku

算額(さんがく) 算額とは、江戸時代の日本で、額や絵馬に和算の問題や解法を記して、神社や仏閣に奉納したものです。江戸時代中期以降、和算が全国に広まる中で、レベルの高さを周囲に示しつつ、さらなる和算普及を願って奉納された算 … 続きを読む
烏天狗と猪の大絵馬 A great picture tablet of raven long-nosed goblin and a boar

烏天狗と猪の大絵馬 享和3年(1803)9月、白石藩八代の片倉小十郎村典(のちの村嗣)が奉納したものです。縦1.8m×横1.5mの大絵馬で、現在は鹽竈神社博物館に展示されています。 安政7年(1860)2月、十代村景の代 … 続きを読む
太刀銘来国光 Raikunimitsu Sword

太刀銘来国光(たちめいらいくにみつ) 国指定重要文化財 鎌倉末の作品、 長さ二尺七寸六分 (83.6㎝)。 身巾広く腰につよい踏張りがあり、 反りの高い長寸の太刀です。 仙台藩四代藩主の綱村公が初めて領国にはいった延宝3 … 続きを読む
長明燈:ますや燈籠 Chomeito (lantern): Masuya Tourou

長明燈:ますや燈籠(ちょうめいとう:ますやとうろう) 仙台藩御用の米商人大阪升屋山片重芳の寄進です。 重芳を育てた番頭山片蟠桃は 「夢之代」 を著わし近代合理主義の先駆となった大学者で、サシ米検査を無料で引受ける代わりに … 続きを読む
石造りの日時計 Stone sundial

石造りの日時計 「林子平考案日時計」と称される県内最古の日時計で、学友である鹽竈神社の神官藤塚知明が、 寛政4年(1792)に奉献したものです。石盤上にはローマ数字を刻し、「紅毛製大東日」と刻す異国風の珍しい日時計です。 … 続きを読む
表坂石鳥居の扁額 Omotezaka ishi torii (shrine gate) plate

表坂石鳥居の扁額(おもてざかいしとりいのへんがく) 「陸奥国一宮」の扁額は、姫路藩主酒井雅楽頭(うたのかみ)忠以の筆によるものです。この石鳥居は寛文の造営時に寄進されたもので、柱には「鹽竈大明神奉創建石華表一基」「寛文三 … 続きを読む
文治鉄灯 Bunji metal lantern

文治鉄灯(ぶんじてっとう) 扉に「文治三年七月十日和泉三郎忠衡敬白」と銘文が浮き彫りされ、平泉藤原秀衡の三男忠衡寄進の鉄灯。 芭蕉翁もこの鉄灯を見て感涙したことが知られますが、当時は宝燈形式であり、屋根、扉は後世の補修で … 続きを読む